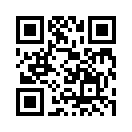› 美しいふすまをつくります。 › 茶室の太鼓襖 茶道口・給仕口・洞庫
› 美しいふすまをつくります。 › 茶室の太鼓襖 茶道口・給仕口・洞庫2010年01月16日
茶室の太鼓襖 茶道口・給仕口・洞庫
茶室の茶道口と給仕口、また洞庫にも椽(ふち)のない襖[太鼓襖」が使われます。
引手は金物などを使わずに、和紙を張り込んだ「切り引手」にします。
装飾性を排除した、わびた風情のある襖です。

方立口の茶道口と火灯口の給仕口
〈襖の寸法〉は普通の襖より小さく、
茶道口は高さ5尺2寸(約158cm)×幅2尺2寸(約67cm)
給仕口は高さを抑えて高さ4尺3寸(約130cm)
〈切り引手の位置〉も茶室側が下から4コマ目、水屋側は下から5コマ目が
一般的です。
座して襖の開け閉めをするので引手の位置は、普通の襖より低くなっています。
〈襖の榾〉は、竪ぼね3本、横ぼね13本で補強のため通常のほねより2本多く
します。
〈すり桟〉が、上張りの和紙が傷まないように太鼓襖の天地に打付けられています。
すり桟の材は杉が一般的で、他にはへり難くて長持ちする、桐や桧が使われます。

太鼓襖の洞庫
〈下張り和紙〉伝統的な襖の下張りと同じで7遍張りくらいです。。
〈上張り和紙〉鳥の子、奉書紙、清張紙などの丈夫で上等な和紙を使います。
重ねしろ3分(9mm)で張り継ぐ「千鳥張り」が伝統的な方法ですが、現代では
3×6判 の一枚張りも見られます。
茶室の意匠については、流派の好みがありますのでご注意下さい。
❖茶道口 亭主が点前をするための出入口
❖給仕口 客座へ直接給仕をする出入口
❖洞庫 道具畳の勝手付につくられた押入式の棚。点前座から亭主が使用できる
ように考案されたもの。
襖designでは、茶室に使用する鳥の子、奉書紙、湊紙、手漉障子紙、茶室金物、
引手を取り揃えています。
また、茶室を得意とする熟練した職人が施工も承ります。お問合せ下さい。
お問合せ fusumadesign@f2.dion.ne.jp
公式サイトはこちら!
http://www.fusumadesign.com
引手は金物などを使わずに、和紙を張り込んだ「切り引手」にします。
装飾性を排除した、わびた風情のある襖です。

方立口の茶道口と火灯口の給仕口
〈襖の寸法〉は普通の襖より小さく、
茶道口は高さ5尺2寸(約158cm)×幅2尺2寸(約67cm)
給仕口は高さを抑えて高さ4尺3寸(約130cm)
〈切り引手の位置〉も茶室側が下から4コマ目、水屋側は下から5コマ目が
一般的です。
座して襖の開け閉めをするので引手の位置は、普通の襖より低くなっています。
〈襖の榾〉は、竪ぼね3本、横ぼね13本で補強のため通常のほねより2本多く
します。
〈すり桟〉が、上張りの和紙が傷まないように太鼓襖の天地に打付けられています。
すり桟の材は杉が一般的で、他にはへり難くて長持ちする、桐や桧が使われます。

〈下張り和紙〉伝統的な襖の下張りと同じで7遍張りくらいです。。
〈上張り和紙〉鳥の子、奉書紙、清張紙などの丈夫で上等な和紙を使います。
重ねしろ3分(9mm)で張り継ぐ「千鳥張り」が伝統的な方法ですが、現代では
3×6判 の一枚張りも見られます。
茶室の意匠については、流派の好みがありますのでご注意下さい。
❖茶道口 亭主が点前をするための出入口
❖給仕口 客座へ直接給仕をする出入口
❖洞庫 道具畳の勝手付につくられた押入式の棚。点前座から亭主が使用できる
ように考案されたもの。
襖designでは、茶室に使用する鳥の子、奉書紙、湊紙、手漉障子紙、茶室金物、
引手を取り揃えています。
また、茶室を得意とする熟練した職人が施工も承ります。お問合せ下さい。
お問合せ fusumadesign@f2.dion.ne.jp
公式サイトはこちら!
http://www.fusumadesign.com
Posted by fusuma at 19:44│Comments(0)